



苛性カリを油と混ぜると苛性ソーダと同じように鹸化という化学変化を起こします。石鹸ができる時の化学変化では苛性ソーダや苛性カリの中にあるナトリウムやカリウムと油の中にある脂肪酸の部分が反応して石けん成分を作ります。この成分にナトリウムが含まれているか、カリウムが含まれているかの違いが使う薬品の違いになります。
泡が立つとか、汚れを落とすといった性質は全く同じなのですが、ナトリウムの石けんとカリウムの石けんではやはり細かいところでは性質が若干異なります。
特に、脂肪酸とカリウムが反応してできた石鹸成分はナトリウムが反応してできたものより水に溶けやすい性質があります。そこで、カリウムの石けんは水に溶かして作る液体石けんやクリーム状の石けんに使われることが多いのです。
確かに苛性ソーダで作った石鹸を水に溶かしても液体状の石鹸ができるかも知れませんが、どろどろになって、使い心地は良くありません。さらに、水分が飛んでしまえば、使い勝手の悪い石けんになってしまいます。そのため、苛性ソーダは主に固形石鹸を作る時に使われることが多いです。
ということで、石鹸の形状を考え、苛性ソーダで石鹸を作るか、苛性カリを使って石鹸を作るかを考えます。中にはミックスして作られる方もいらっしゃるよう。私はこれから、その検証も少しずつやってみたいと思っています。

この苛性ソーダは化学系の私にとっては、実験ではおなじみの薬品の一つです。ちなみに私たちは苛性ソーダとは呼ばず、普段は水酸化ナトリウムといいます。
こちらの名前が正式名称。化学式はNaOH。
昔覚えた記憶がおありの方もいらっしゃるのでは?
この薬品は小・中学生の実験にも登場するくらい、本当にポピュラーな薬品ですが、この苛性ソーダは劇物。扱いには注意が必要です。
食塩を扱うようにはいきません。
苛性ソーダは水に溶けると強いアルカリ性を示すのが大きな特徴です。アルカリ性の物質にはタンパク質を変質する性質があります。
そのため、アルカリ性の物質を皮膚につけるとぬるぬるします。
(石鹸で手を洗うとぬるぬるするでしょ?)
強いアルカリ性の水酸化ナトリウムが皮膚につけば、皮膚のタンパク質を変質させ、大きなダメージがあることもおわかりいただけるでしょう。また、完全に除去しないと、深部を侵すこともあります。特に目の中に入ってしまうと、失明などの恐れもあり、取り扱いには要注意です。
また、苛性ソーダは水分を吸収しやすい薬品で、空気中に置いておくと数分でべたべたになってしまうほどです。
苛性ソーダの保存法にも気をつかうことが必要です。
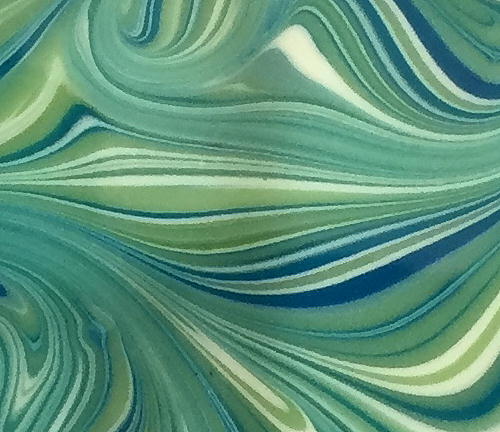
そのため、まずは油が必要です。
基本的にはどんな油でも石鹸にすることができます。しかし、酸化しやすいオイルは石鹸になって化学変化してしまっても、その一部に酸素を取り込み酸化し、油くさいにおいを放ったりします。
そのため、石鹸にはむかないものもあります。
私はコールドプロセス法という方法で作っているため、1ヶ月以上の熟成期間が必要です。時間をかけて石鹸にするので、その間にも酸化が進んでしまいます。また、かといって、ホットプロセス法では加熱に弱い油は使えません。
これらの条件をクリアできるオイルが石鹸に適しているオイルと言えると思います。
また、オイルによっても石鹸のできが違うため。どのオイルを使うかは好き好き。
ちなみに私はひまわりオイル(オレインリッチ),ラード、つばき油が好み。
特にラードは動物性で何となく敬遠する方も多いようなのですが、安価で、できあがりの石鹸はとってもなめらか。
ラード自身、お肌にはとってもやさしい、バランスの取れたオイルなので、愛用してます。